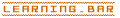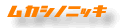実践家はなぜ「研究知見」をスルーするのか?:理論と実践の「死の谷」めぐる罵声の根拠!?
僕の専門分野は、いわゆる「実践現場をもつ学問」です。人材開発は「研究」として存在している「以前」に、それとは無縁の、より多くの人々が日々取り組んでいる「社会的実践」です。
それが人材開発であるかどうかについて、意識するかしないかは別にせよ、複数の人々がある目標を達成するときに、能力やスキルを発揮させる環境をいかにつくるかは、人々の大きな関心事です。
といいましょうか、、、ある程度のスパンと規模をもつ事業を継続させ、何かを成し遂げるためには、それを考えざるを得ないのです。
研究より「以前」に、「実践」があります。
むしろ、人材開発が、ひとつの研究領域として浮かび上がる、ずっとずっと昔から、人材開発という営為は有史以来連綿と続いてきました。この歴史の詳細については、先だっての大学院の授業でやったので、ここでは繰り返しません。
▼
ところで、「実践現場をもつ学問」とは、ある「十字架」を背負っています。
それは、単に「研究知見」を生み出し、研究者のあいだで流通させればよいということではないという「十字架」です。
願わくば、せっかく生まれた「研究の知見をいかに実践に活かしていくのか」ということが問われます。要するに「研究知見をいかに現場にかえすのか?」ということです。この一連の難問に対して、なんらかの答えや示唆を与えることが期待されるのです。
もちろん、すべての研究が、現場の実践者に「かえらなければならない」というわけではありません。中には「基礎的な分野」もあるでしょうし、分野によっては、そういう「研究と実践」の循環を想定しなくても、学問の存在意義を認められている領域というものも、存在するのかもしれません。それは個々の研究者が判断すればよろしい。
ちなみに、一言だけ申し上げますが、「基礎的」というからには、本当に「人間の根源的な問い」に向き合っていることが担保されなければなりません。そうしたものは、当然、高い評価を受けており、たとえば各種の図書賞、学術賞を授与している可能性も高いでしょうし、トップジャーナルでも評価されていることでしょう。
「基礎的だからオレには関係ない」という文言は、時に「基礎的でもなんでもない、しかも、実践にもかえらない研究」を自己正当化するロジックとして巧妙に利用される傾向があるから、わたしたちは注意ぶかくこれを見つめなければなりません。
話を元に戻します。
もちろん、「実践現場をもつ学問」のすべての研究が現場に返らなくてもいい。しかし、「実践現場をもつ学問」の多くの研究領域は、そうではありません。
「研究知見をいかに現場にかえすのか」というダイレクトな問いまでいかなくても、せめて、「あなたは研究者として現場の実践にどのようにかかわるのか?」くらいは考えておく必要があります。
▼
しかし、一般に、生まれた研究知見が実践現場にただちに返ることを夢想できるほど、世の中はあまくありません。実践と現場には「死の谷」よりも深い「断絶」が横たわっているのです。
そして、研究者の中には、「死の谷」の存在を嘆き、「谷の片側」にいながら、「もう片方にいる実務家」に「罵声」を投げかけるものもいます。
こうした領域の研究書・学術書を読んでいると、「罵声」がオンパレードで登場します。
曰く、
実務家は、あいもかわらず、「ほにゃらら研究」の知見を知ろうともしないし、活用すらしない。だから、実務はだめなのだ。
メディアは、「ちょめちょめ学」の知見を配慮しようともしない。「ちょめちょめ学」の知見を正しく伝えないからダメなのだ。
実務は、「ちょめちょめ研究」の知見と離れて行われており、けしからん。「ちょめちょめ研究」の知見をもっと勉強して実践をなすべきだ。
領域にもよりますが、「死の谷」が深く、しかも、研究者側が自らの権力を誇示している領域ほど、この「罵声」は強くなる傾向があります。
「実務」から遠いところにある研究の知見」が活かされていないこと、知られていないことをもって、実践者や実務家を「非難」しているのです。
もちろん、実際は、その「罵声」は実務家には届いていません。
研究者しかよまない専門書の中で、研究者同士で、罵声を消費しているだけです。そして多くの場合、罵声の生産者は、そのことをよく熟知している。「死の谷」の向こうには、届いていないことを前提に、片側に対して「罵声」を浴びせるのですから、要するに、これは「ドラマトゥルギー」です。わたしたちは、そのようなパフォーマンスを相対化する冷静な目をもちたいものです。
だって、罵声が本当に「実践者」に「届いて」しまったとしたら、ケンカになってしまうでしょう?
届かせたいと願いつつも、心の中で、届かないことを夢想する。それが証拠に、この罵声は、僕が学生の頃から、ずっと同じトーンで「死の谷」にこだましています。つまり、「何ひとつかわっていない」。物事を変えたいのだけれども、一方で、変わらないことをよしとする。こうした相反する感情の中に、罵声の主はいます。
▼
ちなみに、この問題に関しての僕の認識は、むしろ「逆」です。
それはワンセンテンスで申し上げますと、「実務」や「実践」は、研究「以前」から存在していたし、「研究がなく」ても、今後も連綿と継続する、という事実を受け入れるところからはじまります。
その上で、
実務が「ほにゃらら研究」の知見を知らないのは、研究者が届けるメディアや機会をもとうとしないからだ。あるいは、「ほにゃらら研究」の知見そのものが、実務と遠く離れている可能性があるからだ
メディアは、たしかに一面的に物事を切り取る。しかし、メディアなどが過剰に「ちょめちょめ学」の知見を無視するのは、「ちょめちょめ学」の存在すら知らないからであり、場合によっては、その学問特有の問題の切り取り方が、環境変化にあっていないと考えているからではないか
「ちょめちょめ研究」の知見と離れておこなれる「実務」が存在するのは、そもそもアタリマエだ。問われるべきは、「ちょめちょめ研究」が実務とは全く無縁の問題の切り取り方をしていることではないか
僕だったら、こう考えます。
要するに、僕だったら、それらの事態で自己内省を行わなければならない対象は、「研究知見の生産者」であると考えます。
この場に及んで、いったい、誰に対して、文句を垂れているんだか(笑)
まずは、「自分が生み出したもの」が「届かないこと」の理由を「自分事」として引き受けることからはじめたいものです。
▼
研究と実践ー今日は、週の頭から、なかなかヘビーなことを考えました。
この問題は、研究領域によっても一概にいえないので、なかなか書くことが難しいですが、僕の認識は以上です。
僕は、
自分の研究が、明日突然、この世からなくなったとしても、実践は、あいかわらず継続するという事実
を抱きしめることから、まずはすべての思考をスタートします。
そのうえで、実務家でも、メディアでもなく、まずは「自分」に何ができるかを考えたいと思います。それが実践に対する、僕の研究のスタンスです。
そして人生は続く
投稿者 jun : 2015年4月27日 06:06
【前の記事へ移動: 「−1から1へのリーダーシップ」:痛みをともなう「立て直し」の経験 ...】【次の記事へ移動: 「もうひとつの子ども時代」でカブトムシを育てる!? 】