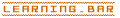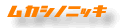「経験学習」の中身を探る
4月も、はやいもので、もう中盤。新年度の慌ただしさが今週あたりで一段落するんじゃなかろうか、という「淡い期待」のもと、激しく動きまわっております。大学院のゼミや授業も、2週目にはいってきて、いよいよ本格化してきました。
今年の大学院中原ゼミでは、Reynolds, M. and Vince, R.さんらが編集した「The Handbook of Experiential Learning and Management Education」を、中原ゼミの大学院生の皆さんで読み、議論をしています。本書は、タイトルが「モロ」に示すように、「Experiential Learning(経験学習)」に関する論文を集めたハンドブックになっています。
この領域の研究者ならば「Reynoldsさん」「Vinceさん」の名前をみた瞬間に、少し「ピン」とくるものがあるはずです。いわゆるランカスター学派! 彼らも批判理論系・ポストモダン系の研究者ですので、本書も、少し「癖の強い本」になっています。
ニュートラルで、プラクティカルな、いわゆる経験学習理論を知りたい方には、あまり向いていません。「経験と学習」の関係について、ドロドロで生々しい内容を含む、マニアックな議論をしたい方向けの専門書だと僕は思います。
▼
大学院ゼミで、なぜこの本を読もうと思ったかというと、最近、僕は「経験学習」という概念で指し示されるものの「多様性」について知りたいと思っているからです。間違って欲しくないのは「経験学習が嫌い」なわけでも、「経験から学ぶことがパワフルではない!」と言いたいわけでは断じてありません。
そうではなくて、日本語でいえば、一口に「経験学習」と呼ばれているものの中に、いくつかの理論的系譜が存在することに、薄々気づきつつも、そのルーツや理論間の布置が、いまだに自分としてつかめていないだけに、少し「気持ち悪さ」を感じているのです。ひと言でいうと「それが知りたい!」。本書を選んだ理由は、それ以上でも、以下でもありません。
▼
「経験学習」という言葉は、多種多様なものを飲み込む「マジックワード」のように感じます。
僕がざっと思いつくだけでも、経営学習研究の中では、様々な「経験と学習の理論」が、同じ「経験学習」というワードの中で、ひとくくりに語られている傾向があります。
たとえば、すぐに思いつくのは「Experiential Learning」の理論的系譜。こちらは、場合によって「体験学習」と訳されることもあります。キーワードは「非日常性」と「教育的意図を埋め込まれた活動」と「感情」と「内省」。
非日常的な空間や場所に参加者を集め、そこで、ある「教育的意図を埋め込まれた活動やコミュニケーション」に従事させます。ここで従事する活動は、時に、情報遮断・感覚遮断を含むような、「日常との隔絶された特異な活動」であることがあります。この「特異な活動」に対して、人々は、試行錯誤しつつ、取り組みます。その場は、「擬似的な民主制(人々の間で駆動する権力を無化することはできないにせよ、この場では民主的に活動しようというルール)」と「今、ここ(Now and Hereにおこる出来事を大切にしよう)」という価値観によって守られた空間になっています。
「Experiential Learning」の現場は、守られた空間ではありますが、「リスキーな空間」でもあります。そこでは、「隠されてきた自分の日常」が逆照射されることもあり、場合によっては、「とんでもないもの」を見てしまう可能性もあります。そうした場合、学習者ないしは参加者は「感情の揺れ」を経験します。最後は、その活動自体を内省し、学習を達成します。
▼
もうひとつの理論的系譜は「Learning from Experience」の理論的系譜です。
こちらは、もともとは経営学の中の、リーダーシップ開発論(Leadership Development Theory)の議論の中から出てきた概念だと思います。成功したビジネスパーソンに回顧的インタビューを行い、自分を一回り大きく成長させた「経験」を抽出するという研究方法論から派生してきた議論で、Ledershipの発達のためには、「経験」、しかも「とびきりの苦難を含んだ経験(俗にいえば、マジで死ぬかと思った苦しい経験)」こそが重要である、という議論を行います。
先ほどの「Experiential Learning」との違いをいくつか述べるとするならば(両者は、全く異なりますけれども・・・)、この言説空間には「民主制(平等性)」というものは存在していません。むしろ、ここで「学ぶべき主体」は、「経験を付与するに足るような能力・アスピレーションをもつ選択された主体(エリート)」です。学ぶべき場所も「非日常の守られた空間」というわけではなく、「権力が作動する日常的な実空間」ということになります。平たく言えば、「将来を嘱望される特権的な能力をもつ主体」を、いかに実空間において伸ばすか、という議論になります。
あと、多くの経験学習論には、共通する価値として「内省」が大切にされているのですが、実は「Learning from Experience」論には、もともと「内省」の概念はありません。というよりも内省よりは「経験のクオリティ」の方にスポットライトが当たっています。具体的には、「とびきりの苦難を含んだ経験」が会社の戦略にしたがって、計画的に付与されることが主張されています。「とびきりの苦難を含んだ経験」を付与される主体には、メンタリングの機会などが必要であることも述べられています。
▼
もうひとつの理論的系譜は、もっともよく知られているKolb, D.の「経験学習サイクル論」です。
Kolb, D.のモデルは、ビジネスの世界でもっとも知られているモデルですが、興味深いことに、教育の世界、学習論の世界ではほとんど知られていません(実際、僕も、経営と学習の研究をするまで知りませんでした)。ビジネスの世界で知られるようになった理由は、こちらの「サイクル論」が「Kolbの創始したオリジナルの理論」というよりも、むしろ、「デューイの理論を解釈しなおした理論」であったからだと思います。教育の世界では、ジョン・デューイそのひとが、よく知られています。
先にも述べましたように、Kolbの源流は、プラグマティズム、具体的にはジョン・デューイの「経験」と「反省的思考」にさかのぼることができるものと思います。デューイの経験と反省的思考の概念を、2次元のサイクル論として表現し、ビジネスの世界に普及させたというのが、Kolb.の業績なのかな、と思います。
ところで、デューイに影響を受けて、仕事の研究をしたもうひとりの研究者に、ドナルド・ショーンがいます。ショーンは、もともと博士論文でデューイの研究をしていました。しかし、彼の省察概念は、デューイ的でも、コルブ的でもない「刹那的かつインプロ的」なものです。実践の「あと」に行われる内省でなく、実践の「まさにそのどまん中」でそのつどそのつど、アドホックに行われ、実践を組み立て直すような省察に、彼は焦点をあて、それを専門性発達の議論に結びつけました。ショーンは経験学習サイクル論とは異なった独自の立ち位置を保ちますが、しかし、この領域において、ジョン・デューイという同じルーツをもつことは、意外に知られていません。
▼
以上、ざっと見てみましたが、まだまだ細かいことをいえば、「経験学習」の言葉には、たくさんの異なった理論的系譜をもった議論が含み混まれています。「経験学習」という言葉で、ひとつの、体系だった理論を想定することはできません。実は、その内部は、本当に複雑に入り組んでおり、ドロドロなのです。
この種の細かい議論は、実務を行う上では、どうでもいいことなのかもしれません。
そんな細かいこと、どうでもいいよ(笑)。
でも、アカデミックには、やはり気になります。一見、どの理論的系譜も「経験学習」という「ひとつの風呂敷」でくるまれてしまいそうなのですが、せっかく、大学院ゼミで、経験学習について多角的にアプローチする機会を持ちましたので、このあたりを「解剖」していきたい、と個人的には思っています。
今日の話は、マニアックでしたね。
そして人生は続く。
投稿者 jun : 2013年4月18日 06:45
【前の記事へ移動: 快適空間、背伸び空間、混乱空間・・・あなたが今立っているのはどの空間?:学びとリ ...】【次の記事へ移動: 状況に埋め込まれたプレゼンスキル : プレゼンの猛者が、所かわれば、派手ゴケする ...】