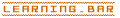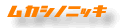ある日突然、学費が100万円あがったとしたら:堤未果著「貧困大国アメリカ2」を読んだ!
「もうこれ以上、我慢ができません。学費を払うために、すでに仕事を3つ掛け持ちしているのです。さらに年間1万ドル(100万円)の値上げだなんて、絶対に無理です」
「学校側は5億3500万ドルの財政赤字を埋めるためだといって、教員2000人の解雇と授業数の削減をするつもりでいるんです。すでに教員の給与は半額にされているのに」
▼
堤未果著「貧困大国アメリカ2」(岩波新書)を読んだ。
新自由主義の思想のもと、企業と政府が癒着するといった、いわゆるコーポラティズムが進行し、教育・社会福祉・医療といった部分に、壊滅的な打撃が加えられ、中流家庭が苦しむ、米国の様子が描かれている。数年前に出版された「貧困大国アメリカ」の続編である。
新自由主義とは、鈴木(2009)を参考にすれば、
1)市場原理主義(市場に任せれば万事うまくいくという考え)
2)企業中心主義(雇用の流動化・雇用の調整をすすめ、株主と経営者への価値を最大化する経営を行う)
3)反福祉国家(福祉は国へのたかりを生むので削減する)
4)グローバル化(市場原理主義を他の国にもすすめる考え)
などを特徴としてもつ考えだという。僕としては、これに5)自己選択・自己決定・自己責任論(すべての社会的不利益・利益は、自己選択・自己決定・自己責任の果てに怒っているとする考え)を加えて、それとしたい。
もちろん、本書で描かれている内容が、どの程度、全体を表しているのか、僕は専門ではないので判断しかねる。著者はリベラリストの立場から、ジャーナリストとしての筆致で、この書籍を執筆しているので、違った見方や表現もあることだろう。この点に関しては、メディアリテラシーの観点から、本書を批判的に読み解く必要があると思う。
しかし、その可能性を差し引いたとしても、本書の問題提起は大きい。とても、人ごととは思えないショッキングな内容に、正直に言葉を失った。以下、本書を適宜引用しつつ、紹介する。
▼
例えば、教育では、大学の学費が取り上げられている。
1990年以降、米国の大学の学費は年々上昇し、毎年5%から10%の上昇をみせている。例えば、アメリカ国内の大学生の76%が通う公立大学に関しては、1995年と2005年比較で、59%の上昇が認められる、という。
この背景には、1)新自由主義のもと、公教育に対する政府支出が大幅に引き下げられたこと、2)競争的資金を獲得するため、著名な大学教員の引き抜きが行われていること、などがある。
一方、マイノリティ、中流家庭が進学の際に頼りにしていた公的奨学金は、段階的に縮小しつづけた。現在、授業料の33%しかカバーできていない状況である。
かつて言われていた「米国には奨学金制度が充実している」という我々のイメージは、決して、十分に機能している状況とはいえない。
かわりに出てきたのが、民間株式会社の提供する「学資ローン」だった。
「教育は社会のために存在するのではなく、個人のためであるから、自己負担せよ」という新自由主義の思想に後押しされ、1980年から、学資ローンは急拡大する。もともとは国が運営していたものが、民営化され、サービスが急拡大した。しかし、これが問題の発端である。
学資ローンの利率は、年率20%弱のところもあるという。
「わたしが学生だった頃、通っていた州立大学の学費は無料でした。今、UCに行ったわたしの娘と息子は、それぞれ4万ドル以上の学資ローンを抱えています。18%というクレジットカード並みの利息でね」
決して、低いとは言えない利率なのに、「大学教育を受ければよい仕事が見つかる」というアメリカンドリームに魅せられた中流家庭、若年層は、何のためらいもなく、契約書にサインをする。
メタフォリカルに言うのならば、彼らの眼前には「契約書」は見えていない。眼前には、大学教育を受けたあとに待っている「成功の夢」が広がっている。
しかし、多くの人々が抱くアメリカンドリームは、泡沫(うたかた)に消える。リーマンショック後、大学教育を受けても、決して、よい仕事につけるわけではない。さほど年収が高くない職業にしかつけなかった場合、高いインフレ率、高い借金の利率によって、すぐに生活は困窮する。
しかし、この学資ローンは、度重なる法律の改定によって、1)借り換えはできない、2)自己破産における借金の残高免責もない、3)消費者保護法の範疇にもはいっていない。
高い利率のもとで、一度でも返済ができなかった場合は、全額返済を迫られ、追いつめられていく。
支払い猶予の申請をたらい回しにされたあげく、1日に何度も何度も矢のような借金の催促が債務者をおそう。預金を差し押さえられ、カードをとりあげられる。クレジットカードがIDとして機能するアメリカにおいて、カードがなくなることほど重大なことはない。あとは、滑り台を転げ落ちるように、社会の最下層に転じる。
アメリカ教育省のデータによると、現在不良債権化した学資ローンの数は全米で約500万件。金額に換算すると、総額400億ドル(4兆円!)だという。
一言でいおう。
これは、要するに「教育版サブプライム問題」なのだ。
本来、教育機会の平等をうたって設立された制度が、逆機能をはたし、国の教育予算を減らし、それが大学の学費を押し上げ、人々を苦しめていくことに加担する。
▼
これは現段階では、「海の向こう」のことである。
しかし、あらゆる物事がそうであるように、米国の今は、日本の未来につながる可能性が高いように感じる。事実、本邦においても、家庭の経済状況によって、大学教育の進学に不平等や不平等が生じている状況は、かつてから指摘されている。
日本も中曽根政権以降、新自由主義的な制度改革、政策立案がなされている。この国の大学や大学生をとりまく状況は、今後、どのようになっているのか、、、正直に僕は不安を感じた。
▼
「もうこれ以上、我慢ができません。学費を払うために、すでに仕事を3つ掛け持ちしているのです。さらに年間1万ドル(100万円)の値上げだなんて、絶対に無理です」
(p12)
「(中略)学校側は5億3500万ドルの財政赤字を埋めるためだといって、教員2000人の解雇と授業数の削減をするつもりでいるんです。すでに教員の給与は半額にされているのに」
(p12)
冒頭で紹介したのは、2009年11月23日 学費値上げに反対する数千人の学生・教員でキャンパスがロックアウトした UCバークリー校の学生と教員たちの「叫び声」、否、「悲鳴」である。
ちなみに、民間学資ローンのCEOが手にした2005年の年収は、4億5000万ドル(450億円)であった。
投稿者 jun : 2010年2月22日 07:51
【前の記事へ移動: パパの研究は「ブロック」? 】【次の記事へ移動: 最近、OJT(On the job training)が機能しないのはなぜか? ...】