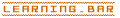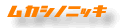「自分ごとだと人は育つ - 博報堂で実践している新入社員OJT」(博報堂大学編)が届いた!
昨日、博報堂大学の白井さんからご著書「自分ごとだと人は育つ」をご恵贈いただきました。
本書は、博報堂で実践している新入社員OJTのお話です。博報堂の考えるOJTのコンセプト、実践の様子をまとめた本です。この「OJT見直しプロジェクト」には、僕も外部からコンサルティングをさせていただいておりました。そのご縁もあって、今回、この本に「解説」を書かせて頂いております。
博報堂大学の方々には1年間にわたる観察・議論の機会をいただき、まことに感謝しております。プロジェクトがスタートしたのは、今から3年前です。僕も、このプロジェクトからはたくさんのことを学ばせて頂きました。後述するように、OJT等の人材育成の仕組みを議論して、作り上げていくプロセスそのものが、そこに関わる人々にとって、学びであったということです。
プロジェクトの途上で、白井剛司さん、田沼泰輔さんはじめ、博報堂大学の多くの方々と議論したこと、そして加藤さんにJoinしてもらい、その対話型研修を観察させていただいたこと、今も印象深く記憶に残っています。心より感謝しております。ありがとうございました。
以下に僕の小論、「解説:人材開発部門発、新たなOJT創造の旅」を掲載させて頂きます。少し長くなりますが、本書の主張や特徴がご理解いただけると思います。どうぞ、ご高覧ください。
--
解説「人材開発部門発、新たなOJT創造の旅」
本書は、株式会社博報堂の人材開発部門(以下、博報堂大学)の方々が、「現在という時代」と「自らの会社の組織文化」の両者にフィットする「OJTの仕組み」を自ら考え、創造していくプロセスと、そこに埋め込まれた各種の人材育成のコンセプトを紹介する本である。
ちょうど、今から3年前。経営学習論(人材育成の科学)を専門とする筆者は、博報堂大学の依頼を受け、外部のアドバイザーとして、このプロジェクトに参加した。具体的には、各種の研修を参与観察し助言を行ったり、人材開発部の方々との議論に参加して、微力ながらプロジェクトに貢献させていただいた。その後、博報堂大学の方々が、種々の議論を「目に見えるかたち」に昇華し、その成果物の一部として、本書が生まれた。博報堂大学の方々のこれまでの尽力と、そして、本書の誕生を、心より嬉しく思う。社会的意義の高いプロジェクトにお誘いいただいたことに、改めて、心より感謝する次第である。
▼
日本企業の「お家芸」とまでいわれた職場における人材育成 - OJT(On the job training)。それが機能不全に瀕している、という認識が高まってきたのは、2000年代初頭であると記憶している。
ちょうどその頃、バブルからのバックラッシュに苦しむ日本企業は、成果主義の導入、組織のフラット化、雇用の非正規化を進め、結果として、職場メンバーの多忙化、マネジャーのプレーヤー化を招く結果になった。
「外科的手術」に比喩される、それらの施策は、確かに、その時代には必要だったかもしれない。しかし、その「代償」のひとつ - 「職場の人材育成機能の低下」 - は、看過できない大きなものであった。
多くの職場で、これまで自ずと機能していたOJTが問題視されるようになり、若年層の能力形成に陰りがみえはじめるまで、それほど、時間はかからなかった。お家芸だったはずの「OJT」が危機に瀕しているという認識が広まった。
▼
冷静になって考えてみれば、OJTとは、それが奏功するまでに、いくつかの社会的諸条件を必要とする。諸条件を列挙すれば、枚挙に暇がないが、ここで代表的なものをあげるとすれば、以下の2つになる。
第一には、若手 - 先輩社員の両者が、長期にわたって、時間を共有し、若手の直面する教育的瞬間に際して、先輩社員からフィードバックがなされることである。若手--職場メンバーの共有できる時間が多忙化によって減少したり、また育成に関与する職場メンバーが見いだせなかったりして、この条件が毀損されれば、人材育成が、遅かれ早かれ、機能不全に陥ることは明白である。近年の人材育成研究が明らかにするように、「人が成長をとげるためには、自分以外の他者とかかわり、フィードバックを受けること」が必須条件である。これを、「人材育成の職場軸」とよぶことにしよう。
第二に、新人が背伸びをすれば何とか到達可能な「ひとかたまりの仕事(成長に資する、責任ある仕事)」が、適切に現場のマネジャーによって配分されることである。願わくば、全体像や職場の目標を咀嚼し、若手によく理解させたうえで、仕事を分与することが望ましい。実際に若手の細かいケアを行うJOBトレーナーとの連携も不可欠だ。
本書でも既に述べられているとおり「背中を見て育て」という時代は、既に色褪せている。まして、断片化した仕事を、あれこれ、多方面から依頼され、こなしつづける。いつでも先輩社員の尻ぬぐいをさせられている。背伸びのない単純な「やらされ仕事」に長期間従事させられる。こうした環境下においての能力の開花は、実に難しい。能力形成を行うためには、たとえリスキーであっても、「できるかもしれないし、できないかもしれない新人」に、「ひとまとまりの成長をうながす仕事」を段階的に「任せていくこと」が、どうしても必要である。これは先の「人材育成の職場軸」と対応させるのであれば、「経験軸」とでも名付けることができるだろう。
▼
とかく、人材育成とは、よく「畑仕事」のメタファに喩えられる。肥料も栄養分も与えず、下草の処理もせずに(=職場軸も経験軸も不足している状態=人材育成の機能不全状況)、たわわに果実を実らせる農作物(=人材)を放置していても、幸いなことか、不幸なことか、直ちに、枯れることはない。
運がよければ、もしかすると、一度や二度ならば、果実(=成果)を実らせてくれることもあるかもしれない。だから、そこに甘えた場合、短期的には「人材育成をしないこと」が「有望な選択肢」のひとつになりうる。
しかし、長期的には、様々なケアをしないかぎり、農作物は、果実を実らせ続けることは不可能である。枝が枯れたり、根が腐ったり、様々な問題がおそってくる。特に、年単位で人材を見つめるとき、何のケアもなされなかった人材は、やはり伸びない。
断じて述べるが、「経験軸」も「職場軸」も機能していない組織で、人は成長することはない。仕事に熟達させ、組織に適応させるには、先輩からのフィードバック、マネジャーによる適切な目標咀嚼、業務経験がどうしても必要になるのである。
▼
さて、ここまでを概観してみると、人材開発に興味をもつ私たちは、知らずのうちに「ひとつの重要な岐路」に立っていることに気づかされる。その「岐路」とは、人材育成にとって大切な二軸 - 「職場軸」と「経験軸」 - が、研修場面などのいわゆるフォーマルな学習機会として主に達成されるのではなく、いずれも「日々の仕事を行う仕事の現場」に位置することから生まれている。
すなわち、業務をマネジャーからアレンジされる「経験軸」の表舞台になるのも「日常の仕事の現場」。メンターになるような先輩によるかかわりが存在するのも「現場」なのである。
だとするならば、人材開発部門は、自社の人材育成を、現場の先輩社員やマネジャーにすべて丸投げし、任せておいてもよいだろうか、という問いが生まれてくる。これが「重要な岐路」だ。志と熱意を持たない人材開発部門にとっては、この問いは、自分たちの仕事が増やさないための「都合のよいロジック」としても機能しうる。
しかし、近年の人材開発研究の諸知見は、もちろんのことながら、この「都合のよいロジック」を支持しない。むしろ、人材開発部門は、現場のマネジャー、現場の人材育成のセーフティネットになるような仕組みを構築する支援を行わなければならない、とされている。これからの企業が選ぶべき道は、そちらの道であることを推奨する。
なぜなら、先ほどのメタファで明確なとおり、仕事の現場で、とかく重視されがちな価値観とは「果実をただちに収穫すること」であるからである。これは利益を上げることが企業の責務である以上、否定されるべき類のものではない。どんなに人の問題に心を砕いたとしても、日常の仕事の現場では、それと拮抗する行動原理が駆動することはやむをえない。必要なのは、「定期的な軌道修正」であり、とかく「成果に傾きがちな意識の補正」を外部から為すことである。
また、職場のマネジャーや経験ある既存メンバーは、「人材育成の原理や理論」を必ずしも把握しているわけではないし、教育的マインドをもって人に接することに得意なわけでもない。よって、人材育成を行うにあたっては、自らの被教育経験を再生産してしまいがちである。特に、そのマネジャーやメンバーが、「自分としては上位者に全く育てられた実感がない場合」あるいは「一匹狼的に自分ひとりで成長してきたと考えている場合」、事態はより深刻である。彼 / 彼女は、自分が受けてきた経験を、他者にもあてはめ、これを再生産してしまう可能性が高いからである。
さらに、職場に人材育成の諸機能をすべて任せてしまうと、組織としては人材にバラツキ(分散)が非常に大きくなることも問題である。ひと言でいえば、育つ職場は人が育つが、そうでないところは、離職やメンタルの問題が噴出する。こういう事態が継続すれば、組織としては、体を為さなくなってしまう。
よって、人材開発部門が、自らの専門性、知見をフルに動員して、人材育成の方針(ビジョン)を示し、必要に応じて職場のマネジャーやメンバーを巻き込み、その方針をご理解いただいたうえで、人材育成に従事してもらう環境をつくっていくことが大切になる。
▼
本書は、このような社会的背景、問題関心を踏まえて読み込んでいくと、極めて実践力の高い示唆が得られる、人材育成の実務書であると思う。
まず「自分ごと」として仕事やキャリアをとらえる、という、博報堂らしい「大きなビジョン」は、すべての人材施策の底流をなしている。その上で、従来のOJTが抱える問題を検討し(サークル型OJT)、時代にあったOJTのあり方として「サーチライト型成長モデル」を提案する。
このコンセプトのもと、さらに提案されているのが「任せて・見る」「任せ・きる」といった「内製化された人材育成コンセプト」である。これらは、人材開発部門の方々が議論をつくしてつくりあげたものであるがゆえに、自社の置かれた外部環境と組織内の組織文化に根ざしたものであるし、「経験前の学習」を重視するという現代の若手世代の特徴に根ざしたものである。なにより、人材開発部門の方々が、自ら創造した物であるがゆえに、彼ら自身の中で、もっとも「腹に落ち」、しっくりくるものなのではないだろうか。
畢竟、OJT等の人材育成の仕組みを議論して、作り上げていくプロセスこそが、そこに関係する人々の間に、学びを生み出すのである。かくして生まれた、人材開発部門の組織レベルの学びも、非常に興味深い。
もちろん、当初は、その議論のプロセスは長く、果てしなく、出口のない迷路に迷い込んだかのようにも感じられたかもしれない。しかし、こうした「地道な努力」が実を結ぶことは、暗い話題が少なくない人材マネジメントの言説空間に、久しぶりに「光明」を見た思いがする。
「地に足のつかない、欧米から借りてきた"手法"」が輸入、流通、消費されがちな人材マネジメントの言説空間に、非常に新鮮なインパクトを与えているのではないだろうか。
▼
本書を手に取る読者の皆さんは -本書の購入前にこのページを斜め読みしているあなたも含めて! - この本書に書かれている内容を、まずはご一読いただきたい。著者らの立場にたって、どういうプロセスで、本プロジェクトを実行していったのかを、ぜひ、追体験していただきたい。
そして、そのうえで為すべき事は、本書のアイデアを、そのまま自社にあてはめることでは、断じて「ない」。
むしろ、この書籍をネタに、自社のあり方を見直し、自社に最もフィットしたキーワードや仕組みを考え抜くことであり、自社の人材育成のキーマンたちと、本書をネタに、議論をつくすこと、であり、実際に、議論に方向性がでてきたら、思い切って実践してみることであり、そうして生まれた結果を振り返ることである。そうしたプロセスを、わたしたちは、「学び」とよぶ。
若手や新人などの「第三者」に対して「学び」を促そうとするものは、自らもまた「学ぶ」必要がある。本書で紹介されているOJTの仕組みでは、OJT指導をする側とOJTを受ける側の「学びの連関」についても述べられている。また先ほど述べたように、人材開発部門の方々が、議論をつくし、施策を実行し、振り返りながら、「学び」を新人やOJTに関わる人々に提供しているのも、いわば「学びの連関」だ。
かくのごとく、学びはいつも「メビウスの環」のように相互に連結しているものである。それを切り離して論じたり、実行することはできない。そんな「学びの連関」を、御社にも生み出してみませんか?
▼
最後に、博報堂大学の試みがさらに展開し、同社のビジネスにポジティブなインパクトをもたらすこと、また、本書をお読み頂いた読者のみなさまが、自社と時代に最もフィットして、自らも「腹おち」できる人材育成プロジェクトを「実践」なさることを、心より願っている。
資源が少ない我が国おいて、最も開発が難しく、しかし、それでいて、なかなか他の国が追従できない要因とは、つまるところ「人」であり、我々の能力が開花した先に発揮される「知性」である。
私たちは、私たちの将来のために、
人と知性を信じ、今、為すべきことをなそう。
そうした志ある人と組織に、本書が届くことを願う。
中原 淳
東京大学准教授(経営学習論)
投稿者 jun : 2014年1月14日 14:46
【前の記事へ移動: 「学んでから仕事する」のか「仕事の中で学ぶ」のか?:わたしはまだ「学習モード」で ...】【次の記事へ移動: あなたの組織は「モチ型」ですか「オムスビ型」ですか!? 】