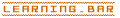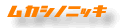組織を外部から支援する者は、「複数の顔」と「マージナル」と「別れ」を生きる!?
Burke, W.(1987)が著したOrganization Developmentを読み返していて、改めて面白いなと思うくだりがありました。ここでは、組織開発を「行動科学の知見を用いて、計画的に組織文化を変革するプロセス」と単純に定義しておきます。難しければ「組織変革」「組織活性化」と考えても問題ないかと思います。
▼
興味深く感じたのは、ODコンサルタント、すなわち、「組織の外部から組織に対して介入を行い変革を援助する人」の役割に関する指摘です。
Burke自身はこう書いているわけではないのですが(正しくいうと、Lippit and Lippit 1978の議論を紹介しています)、僕が、その要旨を、ワンセンテンスで表現するとすれば(ごめんなさい、ワンセンテンスで、でも、時間がないのです)、
1. 組織変革を外部から支援するものは、
たくさんの「顔」を生きる
2. 組織変革を外部から支援するものは、
マージナル(境界)を生きる
ということです。
それに僕がひとつだけ付け加えるのだとしたら、
3. 組織変革を外部から支援するものは、
「別れ」を生きる
というのもあるな、と感じます。
以下、これらについて説明をしていきましょう。
▼
まず、第一に「組織変革を外部から支援するものは、たくさんの「顔」を生きる」とはどういう意味でしょうか。
それは、外部から組織内部に入り込み、様々な支援を行うものは、クライアントのニーズや状況に応じて、1)変革の提唱者、2)技術的専門家、3)教育者・トレーナー、4)協働者、5)代替案提案者、6)プロセスコンサルタント、7)反射鏡といった、様々な役割を演じつつ、介入を行うことを求められる、ということです。
時にエバンジェリストになり、時に、トレーナーとなって研修を行い、時に代案を一緒に考える。そうかと思えば、会議に参加しつつ沈黙を守り、そこで展開される議論のプロセスに傾聴する。
外部から組織内部に介入するものは、そうした複数の多種多様な役割を担わざるをえない、というのが、第一のテーゼです。ここでは「役割」を「顔」と比喩しているのですね。そして、このことは、場合によっては、外部介入者自身の「アイデンティティの揺らぎ」にもつながります。だって、「複数の顔」を生きなければならないんだから。
この第一テーゼは、たとえば、
「外部からの介入者は・・・・・の役割を担うべきである」
という単一の「顔」を想定しがちなこの主の議論へのアンチテーゼです。
たとえば、昨日の話「研究者と実践者」の話に、むりしゃり(方言?)、リンクさせるのなら、「研究ー実践の言説群」の中には、
「研究者は、実践者に対して・・・・の役割を担うべきである」
「研究者は、実践者に教えてはいけないのであーる」
「研究者は、実践者とともに考えるべきである」
という単一の役割を想定した規範的な考え方が存在します。
特に、一度も、実践者と関与した経験がなくて、「研究ー実践の言説群を批評している場合」には、その傾向が強いように感じます。
しかし、現場は、そんなに甘くはありません。状況に応じて、臨機応変に、時には演じることすら求められます。
結局、外部から組織内部にアプローチするときに「単一の顔で、規範的に振る舞おうとすること」は、「顧客志向性」は低いのです。
なぜなら、顧客の状況に「かかわらず」、あるひとつの役割を規範的に演じることが、あらかじめ、決められているのですから。
▼
第二の「組織変革を外部から支援するものは、マージナル(境界)を生きる」とは、どういう意味でしょうか。
それは、外部から内部に介入しようとするものは、一見、内部の人間のふりをしつつ、時には外の人というポジションを活かし、内部の人には言えないことをいうことが求められる、ということです。わたしの言葉でいえば、要するに「知らんぷり」して「刺す」ですね(笑)。
逆に、全く「外の人」と思われると、内部の人からは受け入れてもらえません。よって、他方では「内部の人として、皆さんで頑張っていきましょうや」という風に、演じることが求められます。
結局、そのポジションは、すべてが矛盾しています。内部に染まらないように、内部に入って行かなくてはなりません。そして外部でないふりをして、外部でなければなりません
この状態こそが「マージナル」です。
組織開発を行うものは、内部であって「完全な内部」ではなく、外部であって「完全な外部」ではない、微妙な「境界」を、まさに綱渡りしなくてはなりません。「綱渡り」ってことは、ひと言でいえば「リスキー」だということです。外部からの組織変革とは、まさに「リスクを生きること」でもあります。
▼
第三の「組織開発を行うものは、別れを生きる」とはどういう意味でしょうか。それは、外部から介入するべきものは、最後の最後は、内部の人と「別れる」運命にあるということです。
なぜなら、理想的状態は、内部の人々が、内部を自ら変革し続ける状態を維持するべく、能力や意欲をつけることが大切だからです。
たとえ、外部からの支援によって内部が変わった場合においても、内部の人には、「自分たちが変えたのだ!」と思わせなくてはなりません。また、外部の人は、そのために、内部の人とは「別れなくては」なりません。
組織開発を行うものは、最初から「別れ」を想定して、支援を行わなくてはなりません。
究極をいえば、「自分がいなくても、物事がまわるように、組織内部にキーマンを育成し、仕組みをつくらなくてはならない」ということです。つまり「組織を外部から変革する行為」とは、究極、「介入者である自分」を「消去」する行為でもあります。
▼
今日の話は、組織開発コンサルタントに求められる役割でした。時間が今日は15分しかなく、本当はもっともっと書きたいのですが、このくらいにしておきます。でも、なかなか、考えさせられる読書でした。
特に、昨日、お話ししたような「研究者ー実践者の関係を論じる言説」において、本日のお話しは、示唆は深いと思います。ま、飛躍してるけど、思い切り想像力をたくましくしてよめば、関連づけて考えることもできますね。
今日のお話と昨日の話を関連づけて話すのだとすれば、今日の話は、「研究者ー実践者の関係を論じる言説」においては、ともすれば、「パターナリスティックな価値観」が非常に強くなる傾向があることへのアンチテーゼになるのだと思います。それも一面ではよいことなのですが、あまりに強すぎることは、組織を外部から支援することのリアリティを見失ってしまいがちです。
特に、僕が抵抗があるのは、
「研究者はかくかくしかじかの(理論上想定される)単一な役割で、実践にかかわり、実践者と・・・しなくてはならない」
「研究者は実践者と"ともに"・・・しなければならない」
「研究者は実践に、"ずっと"かかわらなくてはならない」
とかいう、まことに「牧歌的」な批評的言説です。
そう「思いたい」のはわかるし(正しく言うと、「そう思いたいという思いはわかるけど、僕はそう思っていない」)、それを「理想」としたいのはわかるけど(正しく言うと、「それを理想としたいんだろうな、という雰囲気はわかるけど、僕はそれが理想だとは思わない」)、しかし、リアリティはそうではないような気がします。
そうした牧歌的言説は「組織に外部から関わる人」が覚悟し、腹をくくらなくてはならない、もうひとつの「厳しい現実」を忘れがちです。
「たくさんの顔をもち、リスクをとって、マージナルを生き、別れを連続する」というものは、なかなか「厳しい生き方」です。
組織に外部から介入するときに経験するであろう、そういう「リアリティ」を、わたしたちは、意図的に無視することはできません。
そして人生は続く。
投稿者 jun : 2013年11月27日 08:08
【前の記事へ移動: 「研究者ー実務家との関係づくり」の「研究そのもの」っぷり: あんたが実践して、や ...】【次の記事へ移動: わずか13字で「世界」を表現し、人を惹きつける方法!? 】