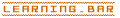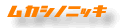官僚制の憂鬱:黒澤明監督「生きる」を見た!
1953年に撮影されたこの映画が、いささかも古く感じられないことが、最もアイロニカルなことではないでしょうか。
この映画が糾弾しているのは、近代に発明された最も合理的な組織原理である「官僚制」。それは、かくもしぶとく、かくも根が深いものなのです。
---
黒澤明監督「生きる」を見ました。
主人公は、30年間無欠勤を続けていた市役所市民課の無気力課長、渡辺です。女性社員につけられたあだ名は「ミイラ」。
冒頭のナレーションでは、渡辺に、辛辣な言葉が浴びせられます。
---
これはこの物語の主人公の胃袋である。
幽門部にガンの兆候が見られるが、
本人はまだそのことを知らない
彼は時間をつぶしているだけだ。
彼には生きた時間がない。
つまり彼は生きているとはいえない。
---
しかし、ある日、渡辺は、自分が胃がんに冒されていることを知ります。余命は半年。
狼狽した渡辺は、遊興にふけります。頼りにできると思っていた息子夫婦は、渡辺の退職金にしか興味がない。小津安二郎の「東京物語」に描かれるような、老人の孤独が、この映画にも漂っています。
渡辺が、仕事と息子のことを語るシーン。渡辺の甘えは、若い女性職員の一言で、バッサリと切り捨てられます。
---
【渡辺】
なぜわたしがミイラのようになって
30年働いたかというと、それは息子のためだ
【女性職員】
それを息子さんのせいにするのはどうかしら
息子さんが、あなたにミイラになってくれ、
と頼んだわけじゃないわ
---
遊興は長くは続きません。かといって、誰を責めるわけにもいきません。息子など当てにはならない。
渡辺は、自分の人生を見直し、「何かをつくること」を決断します。そうだ、カタチになるものをつくるのだ。「公園」をつくろう、と。そして、自分の人生を生きるのだ。
役所のセクショナリズムをこえ、何度も何度も関係課に頭をさげ、暴力団からの脅しにも屈せず、彼は、ついに「公園」をつくります。
できた公園で、彼はブランコにのりながら、死を迎えます。安らかな死を。
---
ここまでもオモシロイのですが、秀逸なのは、ここからでした。
最後は、渡辺の葬儀のシーンなのですが、ここで、市役所の連中が集まってくる。彼らが話しているのは、
「あの公園は誰がつくったのか?」
ということです。
「あの公園は、渡辺さんがつくった」と涙ぐむものがいれば、「予算をとってきたのは公園課なのだから、公園課がつくった」というものもいる。助役などは、選挙をあてこんで、渡辺の業績を横取りします。
中には、「あの公園は、誰がつくったのでもない、偶然できたんですな」という人まででてくる始末です。このやりとり、まぁ、滑稽すぎて苦笑してしまいます。
職員の中には、「私だって昔は・・・」と憤るものもいれば、「ゴミ箱を片付けるのでもね、ゴミ箱いっぱいの書類がいるんだから」とあきらめているものもいる。
結局、その場は「明日から頑張りましょう」ということになって、お開きになるのですが・・・。
しかし、そう簡単には変わらないのです。最終シーンでは、渡辺の後任課長が、市民からの問い合わせや要望を、「たらい回し」にするシーンで終わる。
---
最初にも述べましたとおり、1953年のこの映画のモティーフは、今も、いささかも古く感じられません。ということは、今も、この映画が糾弾している、ある種の弊害は、今もなお、現在進行形で続いているということです。
渡辺の憂鬱は、今を生きる誰かの憂鬱と重なっています。
投稿者 jun : 2007年2月22日 08:38
【前の記事へ移動: わずか10%の可能性でも:OJTなのか、OFF-JTなのか? 】【次の記事へ移動: 手が気になりはじめると自我が生まれる? 】